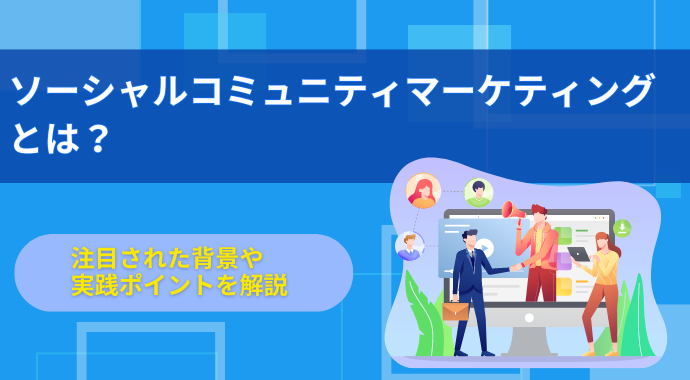ファンコミュニティの立ち上げに挑戦する企業は増えていますが、企画しても「思ったように人が集まらない」「声を活かせない」「社内を巻き込めない」といった壁に直面し、成果が出ないまま終わるケースも少なくありません。
本記事では、良くある失敗事例と立ち上げ時にチェックすべき項目を紹介しながら、コミュニティ立ち上げを成功に導くヒントを解説します。
\ファンマーケティングの始め方を解説/
資料を無料プレゼント中
ファンコミュニティ立ち上げで失敗しがちな3つの落とし穴
- 入口設計が甘く、参加者が集まらない
- 声を活かさず“発信の場”にとどまる
- 部署間の分断で連携がとれず予定通り進まない
入口設計が甘く、参加者が集まらない
多くの企業が「コミュニティを立ち上げれば自然に人が集まる」と考えがちです。
しかし実際には、既存顧客にどう告知し、動機づけるかを設計していないと、誰も参加しない「空っぽの場」になってしまいます。
失敗の背景には、自社商品の魅力をきちんと理解できていないことがあります。
そのため「誰にどう届けるのか」という集客施策を設計できず、結果として成果に結びつきません。
告知の方向がぶれてしまい、参加者数が伸びないまま、半年で投稿が途絶えるケースも見られます。
一方、成功する企業は入口設計を重視しています。
事前の工夫で熱量の高い参加者を先に巻き込み、立ち上げ時点から活気をつくります。
また、単純な人数ではなく「エンゲージ度」をKPIに置き、持続的な参加を促しています。
声を活かさず“発信の場”にとどまる
コミュニティを単なる「企業からのお知らせを流す場所」にしてしまうことも、失敗しがちな落とし穴です。
一方通行のPRが続けば、参加者は「結局宣伝か」と感じて離れていきます。
特に、マーケティング以外の部門が運営を担当すると、ファン心理を理解しないまま進めてしまうケースが見られます。
参加者は単なる告知やPRではなく、自分の声がどのように扱われるかを重視しています。
そのため、コミュニティを成長させるには、ファンの声をどのように収集し、社内で活かすかという仕組みを持つことが不可欠です。
声を活かせる体制があれば、双方向のやりとりが増え、自然に参加者の熱量や発信意欲も高まっていきます。
部署間の分断で連携がとれず予定通り進まない
大企業に多いのが、部門間の分断による停滞です。
マーケティング部がコミュニティを立ち上げても、営業やCS、開発がそれぞれ独自に動き、全体が噛み合わなくなることがあります。
さらに、ナショナルクライアントのように部門意識が強い企業では、「自分の担当領域以外は関与しない」という姿勢が壁になりがちです。
こうした状況では、決裁権を持つ旗振り役が不在のままプロジェクトが進み、意思決定が遅れて時間ばかりが過ぎてしまいます。
この落とし穴を避けるためには、共通の目的や指標を共有することが欠かせません。
組織横断で合意がとれていれば、立ち上げ期の停滞を防ぎ、継続的なコミュニティ運営につなげることができます。
失敗を回避するためのチェック項目
失敗の背景には、担当者が共通して抱える「不安」があります。
これを事前に言語化し、チェック項目として整理することで、失敗の芽を早い段階で潰すことができます。
- 自社の商品を客観的に理解しているか?
- 自社の運営に必要な関係部署を把握できているか?
- 成果を測るための基準を持てているか?
自社の商品を客観的に理解しているか?
ファンコミュニティは「どんな商材に対して、誰が集まるのか」という前提がずれると、そもそも成立しません。
自社商品を主観だけで捉えていると、集客設計やペルソナ設定がずれ、結果として「送客しても参加者が集まらない」という落とし穴に直結します。
商材の武器を外部の人に説明できるレベルで把握しているか――これが最初の分岐点になります。
自社の運営に必要な関係部署を把握できているか?
コミュニティ運営はマーケ部門だけでは機能しません。
営業、CS、開発など複数部門の知見や関与がなければ、ファンの声を活かす仕組みも形骸化します。
さらに、決裁権を持つ旗振り役が不在だと、施策が進まないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
また、実務ではシステムやアカウントの権限管理などで管理部門の承認が必要になるケースも少なくありません。
社内の 承認フローを見落としたまま進めると、施策の開始が遅れたり、実現できない機能が後から判明したりするリスクがあります。
「誰を巻き込み、どの部署に何を担ってもらうか」を初期段階で整理しておくことが重要です。
成果を測るための基準を持てているか?
「何をもって成功とするか」を定義できなければ、コミュニティは迷走します。
参加人数だけをKPIにすると「人は集まったが熱量が低い」という状態に陥りがちです。
エンゲージ度やUGC数など質的な指標を持てば、施策改善の方向性が見えやすくなります。
数値で測れる基準を最初に決めておくことが、担当者の「成果が見えない不安」を解消し、社内で説明責任を果たすための土台になります。
コミュニティ導入支援の事例紹介:課題に応じたカスタマイズ対応
コミュニティ運営を検討する際、企業が抱える課題はさまざまです。
ここでは、導入する企業が直面した課題に対して、実際に行われたサポート事例で代表的なケースを紹介します。
- 送客課題の解決事例|事前ミーティングで参加意識を醸成
- 声の活用課題の解決事例|「中の人セミナー」で双方向発信をレクチャー
送客課題の解決事例|事前ミーティングで参加意識を醸成
ある企業では、コミュニティ立ち上げ直後に「参加者が集まらない」という課題がありました。
そこでDISCO導入時に、事前ファンミーティングを開催。
さらに、コミュニティ名を参加者から募ることで「自分が関与している場」という意識を醸成しました。
その結果、初期参加率が大幅に改善し、熱量の高いファンが中心メンバーとなりました。
声の活用課題の解決事例|「中の人セミナー」で双方向発信をレクチャー
別の企業では、コミュニティが「発信の場」にとどまり、せっかく参加してくれたファンが定着しない問題を抱えていました。
そこで「中の人セミナー」を実施し、ファンと直接接点を持ったことがない社員にもレクチャーをしました。
セミナーでは、「商品を売り込むのではなく体験を共有する」「ファンの発言を否定せず、まず受け止める」「小さな投稿や意見にも感謝を伝える」といった基本姿勢の確認。
さらに、チャットやコメントへの返信例を実演し、「運営側の顔が見える書き方」「共感を示す言葉づかい」を具体的に学ぶ時間も設けています。
こうした取り組みにより、双方向のコミュニケーションが活性化。
UGC投稿数は立ち上げ前の2倍となり、コミュニティがファンの声で自然に育っていく流れが生まれました。
まとめ:落とし穴を避け、不安を解消し、成果を積み上げる
ファンコミュニティ立ち上げには、多くの企業が共通して陥る課題があります。
こうした課題は、チェック項目を押さえ、準備をすることで未然に防ぐことができます。
ただし、課題が発生する根本の原因は企業ごとに異なります。
商材の特性や社内体制、狙うファン層の姿は一社ごとに違うため、チェック項目をなぞるだけでは本質的な解決には至りません。
真の意味でコミュニティ運営を成功させるには、個別の状況に合わせた具体的な対策が必要となります。
Kazeniwaは、そうした個別の課題に応じて伴走し、具体的な打ち手をカスタマイズしてきました。
取り組みを通じて得られた知見をもとに、クライアントにとって最適な「再現性ある成功の型」を育てていくことを目指しています。