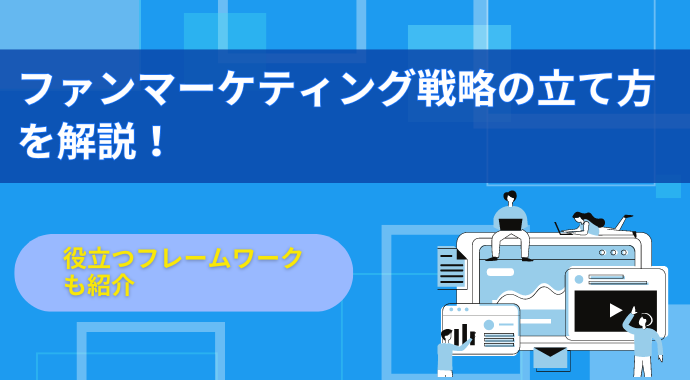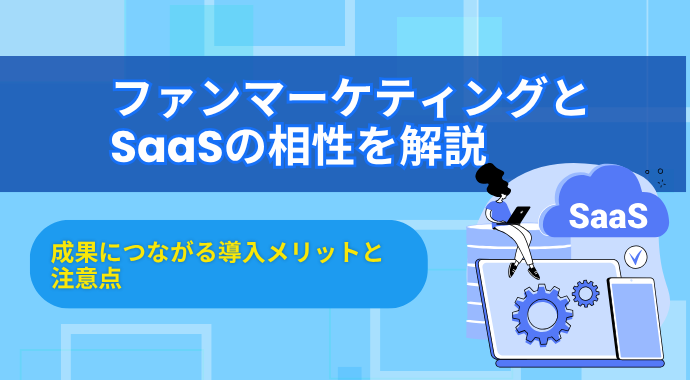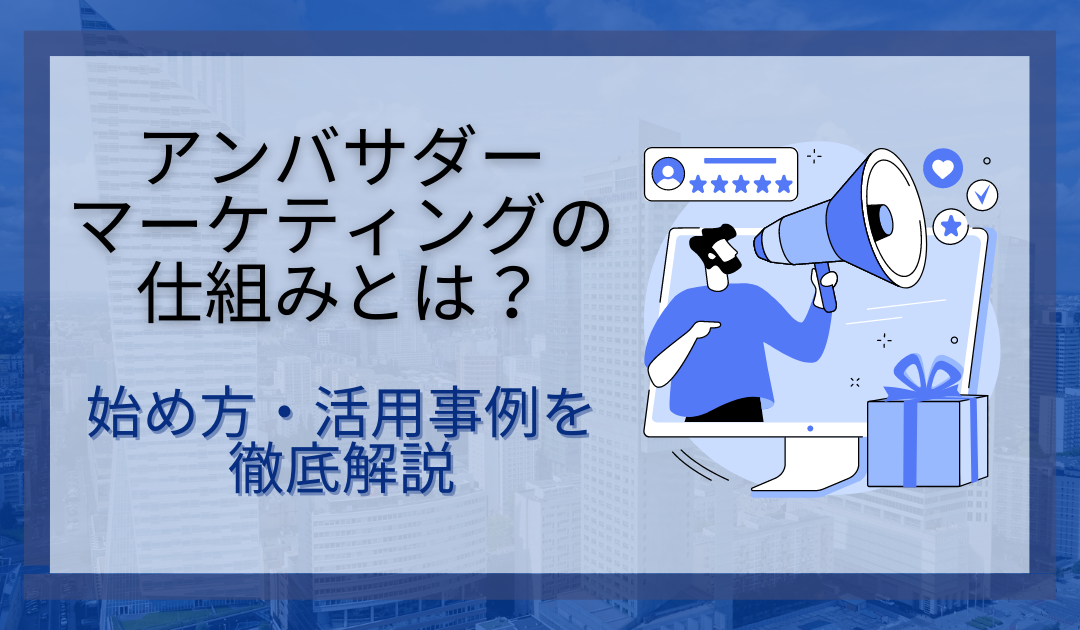小売業が共感の仕組み化を進める中で、メーカーに求められているのは共創の仕組み化です。
本記事では、製造業がファンマーケティングを活かしてブランド価値を高める考え方を解説します。
メーカーにこそファンマーケティングが必要な理由
製造業の市場は、構造的な転換期を迎えています。経済産業省の製造品出荷統計によると、日本の製造業全体の営業利益率は過去10年で約1.5ポイント低下しています。
国内市場の成熟とコスト競争の激化により、製品そのものの差だけでは優位性を保ちにくくなっています。
加えて、OEMやODMなど受託生産の割合が高まっており、BtoB取引では最終顧客との関係が分断されがちです。この構造の中で、自社ブランドを持つメーカーが増加。
2023年には製造業のD2C市場規模が2,300億円を突破し、前年から約18%成長しました。
つまり、誰のためにつくるかを可視化し、共感で選ばれる構造をつくることが、メーカーにとっての新たな競争軸になっています。
関連記事:価値共創マーケティングとは?価値共創がもたらす効果や成功事例、手法を解説!
ファンマーケティングを活かすメーカーの成功事例
ファンマーケティングは、規模を問わず製造業に拡大しています。
ここでは実際に成果を上げている企業の代表的な3つのパターンを紹介します。
- クラウドファンディングを通じた共創型開発
- 職人や開発者が発信するブランド型製造業
- 展示会を発表の場から関係構築の場に変える
クラウドファンディングを通じた共創型開発
試作段階からファンを巻き込み、開発過程を公開する取り組みが増加しています。
クラウドファンディングのプラットフォームMakuakeなどでは、陶磁器メーカーや金属加工業、食品メーカーが試作品を公開し、ユーザーの意見を反映する事例が多数見られます。
製品開発の“透明性”が共感を呼び、発売前からファンベースを形成できるのが特徴です。
職人や開発者が発信するブランド型製造業
家電や文具、日用品などでは、開発者自らがSNSで設計思想や失敗談を語る発信が増えています。
たとえば家電メーカーのバルミューダは「なぜその形状や素材を採用したか」をストーリーで語り、ユーザーが思想に共感して購入する構造を築きました。
製品の性能比較ではなく、ブランド哲学への共感が購買動機になる好例です。
展示会を発表の場から関係構築の場に変える
近年、東京ギフトショーやJAPAN PACKなどでは、来場者が体験・参加できる展示を重視するメーカーが増えています。
単なるカタログ展示ではなく、製品を試せる、担当者と直接話せる設計に変えることで、共感や信頼が生まれます。
これらに共通するのは、製品が完成する前から関係を育てていることです。
ファンマーケティングは「完成品を売る」のではなく、「つくる過程から共感を生む」発想に立っています。
関連記事:【事例付き】ファンマーケティングに向いている商材とは?商材販売のポイントや注意点を解説
ブランドの世界観を共有する仕組みづくり|SNS・EC・展示会
メーカーがファンと関係を築くには、製造・販売・発信をつなげる仕組みが重要です。
具体的には以下の3つの接点を設計軸とします。
- SNSでブランドの背景を発信する
- ECで世界観を体験できる導線を設ける
- 展示会でリアルな共感を生む体験設計
SNSでブランドの背景を発信する
製造現場や素材選定、試作品の改良プロセスなど、メーカーならではの“裏側”を発信することが信頼につながります。
たとえば金属加工メーカーが熟練職人の手仕事を紹介したり、食品メーカーが原材料生産者との取り組みを紹介したりすることで、「この会社なら間違いない」という共感が生まれます。
関連記事:ブランドストーリーテリング。ストーリーで魅せる、ファンの心に響くブランド戦略
ECで世界観を体験できる導線を設ける
D2C展開を行うメーカーでは、単なるカタログ型ECではなく、ブランドストーリーを体験できる設計が重視されています。
製品の背景ページや開発者インタビュー、利用者の声を組み合わせることで、単なるスペック訴求ではなく“思想と体験”を届けることができます。
展示会でリアルな共感を生む体験設計
展示会では、製品を並べて説明するだけでなく、開発担当者が自ら語り、体験できるブース構成にすることがポイントです。
素材の触感を確かめられるコーナーや、試作比較を見せる展示は、メーカーにしかできない体験価値を提供します。
SNS・EC・展示会の発信軸を統一することで、どの接点でも一貫したブランド世界観を伝えられるようになります。
ファンとの共創を実現するプロセス設計|商品開発・UGC・イベント
ファンマーケティングの本質は、共感の先にある共創です。
顧客を巻き込み、製品開発や発信をともに行うことで、関係性は深化します。
- 商品開発にファンの声を反映する
- UGC(ユーザー投稿)を活かした共創
- リアルイベントで参加するブランド体験を設計
商品開発にファンの声を反映する
開発初期からファンを巻き込み、アンケートや試作品体験を通じて意見を反映します。
たとえば、文具メーカーがSNS上で「次に欲しい機能」を投票形式で募集し、その結果を次期モデルに反映する事例があります。
開発の一部を共有することで、ユーザーが「一緒につくっている」感覚を持つようになります。
UGC(ユーザー投稿)を活かした共創
製品を使用するユーザーの投稿(使い方・カスタマイズ)をブランドが拾い上げて紹介することで、コミュニティの活性化が進みます。
特にクラフト・食品・ライフスタイル系メーカーでは、ユーザー投稿が次の企画の着想源になることも多く、SNS分析を通じて新しい商品企画が生まれます。
リアルイベントで参加するブランド体験を設計
工房見学、試作体験、限定イベントなどを通じて、製品を“体感”できる機会をつくることが重要です。
たとえば陶磁器メーカーが釉薬づくり体験を開催したり、家電メーカーが開発チームと対話するイベントを行ったりすることで、ブランドへの信頼と愛着が深まります。
共創の目的は単なる販促ではなく、聴く・反映・共有の循環を生み出すことです。
関連記事:ブランドとファンの距離感とは?ファンと良好な関係を築くための考え方や有効な施策を解説
継続的なファン育成のためのデータ活用とKPI管理
ファンマーケティングの効果を継続的に高めるには、感覚ではなくデータに基づいた改善が欠かせません。
製造業でもCRMやSaaSを活用し、関係の深度を数値で捉える取り組みが広がっています。
- CRMや会員データで誰が共感したかを可視化
- LTV・再購入率・UGC投稿率などをKPIに設定
- SaaSによる自動化とナレッジ共有
CRMや会員データで誰が共感したかを可視化
オンラインストア、展示会、SNSキャンペーンなど、点在する顧客接点を統合し、購買履歴や参加履歴を一元管理します。
たとえば、展示会で名刺交換した顧客が後日ECで購入した場合、その経路を把握することで、営業とマーケティングが連携できます。
LTV・再購入率・UGC投稿率などをKPIに設定
従来の製造KPI(生産量・納期遵守率)だけでなく、関係性の継続を測る指標を組み込みます。
「初回購入から6か月以内の再購入率」「SNS投稿を行ったユーザー割合」などを可視化することで、ファンの熱量を定量評価できます。
SaaSによる自動化とナレッジ共有
MA(マーケティングオートメーション)を活用し、顧客行動を自動トラッキング。製品カタログ閲覧、動画視聴、問い合わせ内容などを統合して、どの情報が共感につながったかを分析します。
この情報を開発・営業・広報が共有することで、組織全体でファンづくりを継続的に進められます。
関連記事:ロイヤルティプログラムとは?導入メリットと6つの類型・成功事例を紹介
製品を超えて関係を設計するメーカーへ
メーカーがファンマーケティングを実践する意義は、製品の差ではなく関係の差をつくることにあります。
共感を集める発信、共創を生む仕組み、データで育てる関係づくり。これらを循環させることで、製品を超えたブランド価値が形成されます。
弊社 Kazeniwa が提供する DISCO では、企業やブランドのファンとの関係構築を支援し、熱量の高いファンの醸成・獲得や、安定した売上基盤の構築をサポートしています。
ファンとの共創を仕組み化し、ものづくりを次のステージへ進めたい方は、ぜひご活用ください。