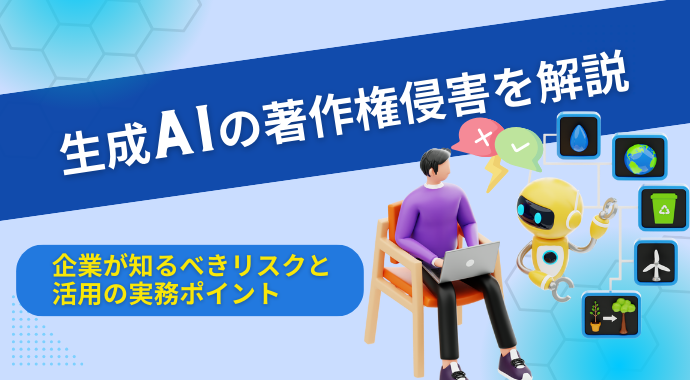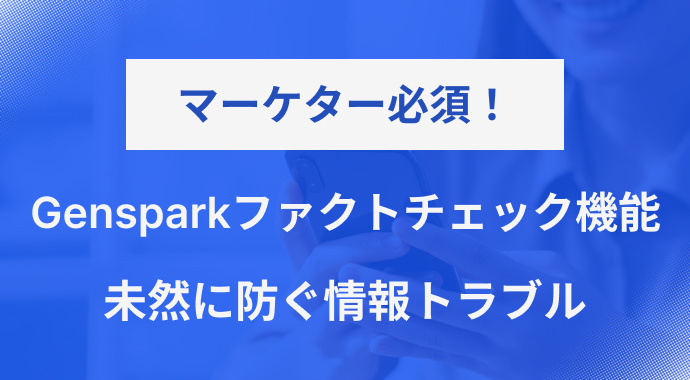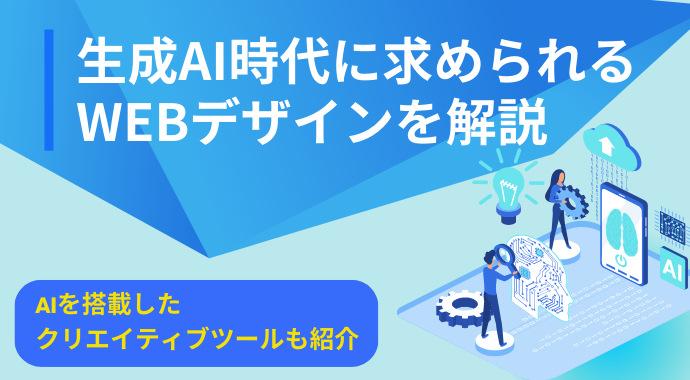ChatGPTや画像生成AIなどの登場で、コンテンツ制作や業務効率化が加速しています。
一方で、企業にとって避けては通れないのが「著作権侵害のリスク」です。
本記事では、「生成AIと著作権侵害の関係」を整理し、企業が実務で活用する際に押さえておきたいリスクと対策のポイントを解説します。
生成AIで作った画像や動画は誰のもの?まず押さえたい法律の基本
画像・映像・音声まで自動生成できるAIツールの進化は目覚ましく、企業や個人でも活用が広がっています。
しかし、生成AIによって作られた画像や動画の「権利」や「所有者」は誰なのか?という問題は、意外と曖昧にされがちです。
まずは以下について押さえておきましょう。
- 著作物とは著作権法で守られる「創作された表現」のこと
- 著作権の例外は一定の条件を満たしたとき
- AI生成物の著作権は創作的寄与をした人のもの
- 文化庁が公表した生成AIに関する著作権上の指針
著作物とは著作権法で守られる「創作された表現」
簡潔に言うと、「人間の思想や感情を、創作的に表現したもの」が著作物とみなされます。
著作権法では以下のようなものが著作物と認められています。
- 文芸 小説、詩、エッセイ、記事、マニュアルなど
- 音楽 作曲、歌詞、楽譜
- 美術 絵画、イラスト、デザイン、書道
- 写真 撮影した写真(創作性のあるもの)
- 映画 映画、アニメ、動画(構成や演出を含む)
- プログラム ソフトウェア、アプリ、ゲームのコードなど
- 舞踊・演劇 振り付け、演劇脚本・演出
- 建築 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
著作権は作品を創作した瞬間に自動的に発生します。
つまり、発表しなくても完成しただけで権利が認められるということです。
ただしトラブル時の証拠として、著作物登録制度(文化庁)を活用するケースもあります。
また著作権には保護される期間(権利が続く年数)は下記のとおりです。
- 保護期間 著作者の死後70年まで(※原則)
- 法人等が著作した場合 公表後70年まで(例:映画会社など)
- 例外・旧作 昔の作品(旧法適用など)では50年のケースも
著作権の例外は一定の条件を満たしたとき
著作権は強力な権利ですが、一定の条件を満たせば、著作物を“許可なく使える”ケースも存在します。
これが「著作権の例外規定」です。
- 私的使用(家庭内など)
- 引用(きちんとルールを守ればOK)
- 教育・学習目的での使用
- 報道・批評・レビュー
- 図書館での複製
- 障害者の情報アクセス支援
AI生成物の著作権は創作的寄与をした人のもの
日本の著作権法では、著作物とは「人間の思想・感情を創作的に表現したもの」と定義されています(著作権法第2条)。
そのため、AIによって完全に自動で生成された画像・文章・音楽には、原則として著作権は認められないと考えられています。
完全な自動生成ではなく、ユーザーがプロンプト(指示文)を工夫したり、生成結果に創作的な加工を加えたりした場合、人間の創作性が認められて著作権が発生する可能性があります。
著作権が認められる例:
- 独自性のあるプロンプトを駆使して生成
- 出力された画像を構成・色彩・構図などを編集
- AI生成の素材を組み合わせて独自の作品を作成
文化庁は、生成AIと著作権の関係について、2024年3月に「AIと著作権に関する考え方」を公表しました。
この文書では、現行の著作権法におけるAI生成物の取り扱いや、著作権侵害のリスクについて整理されています。
とくに以下のようなケースで侵害の可能性があると指摘しています。
- 特定の作家・作品のみを学習させたAIが、酷似した出力を行う場合
- 商用目的で生成AIが“他人の表現”を模倣した画像・文章を使用する場合
これは、AIが「偶然」似たわけではなく、特定の著作物に依拠して生成していると判断された場合、著作権侵害にあたるという考え方です。
事例から見える課題|生成AI×著作権の実際の訴訟・判例
生成AIと著作権をめぐる法的課題は、国内外で注目を集めています。
ここでは実際の訴訟や判例を紹介します。
以下の5つの事例をみていきましょう。
- 大手報道機関が生成AI企業を提訴|著作権侵害をめぐる争点とは
- 画像提供サービス×生成AIの対立|著作権侵害の行方
- 海外AIサービスが日本の著作物に類似画像を生成|著作権侵害と判断された事例
- 音楽生成AIが“酷似”を巡って提訴される|業界全体に波紋
- AI学習に使用された書籍が争点に|大手テック企業に対する著作者の訴訟
大手報道機関が生成AI企業を提訴|著作権侵害をめぐる争点とは
2023年末、海外の大手報道機関が、生成AI開発企業とそのパートナー企業を著作権侵害で提訴しました。
訴えの主な内容は、自社の記事コンテンツが無断で学習データとして使用された点にあり、損害額は数十億ドル規模にのぼると主張されています。
この訴訟は、生成AIの開発過程における著作権侵害リスクが社会問題化した初期事例のひとつとされています。
画像提供サービス×生成AIの対立|著作権侵害の行方
大手画像提供サービス企業が、生成AI開発企業に対して著作権侵害の訴訟を提起。
数百万点以上に及ぶ著作権保護対象の写真素材が無断で使用されたと主張しました。
この訴訟は、生成AIが学習対象とするデータ選定のあり方に対して、初めて本格的な法的課題を突きつけるケースとなりました。
海外AIサービスが日本の著作物に類似画像を生成|著作権侵害と判断された事例
海外のAI開発企業が提供する画像生成サービスにおいて、日本の著名キャラクターに酷似した画像が出力され、著作権侵害と認定されたケースもあります。
裁判所は、生成された画像が原作の創作性を明確に模倣していたと判断し、損害賠償を命じました。
この事例は、AIによる創作物であっても著作権侵害が成立し得ることを示した重要な判例とされています。
音楽生成AIが“酷似”を巡って提訴される|業界全体に波紋
音楽業界大手企業が、音楽生成AIサービスを著作権侵害で提訴しました。
問題視されたのは、生成された楽曲が既存の著作権保護作品に極めて酷似していた点です。
この訴訟は、AIによる音楽生成に関して、業界全体で「著作権と創作性」の線引きを見直す必要性を浮き彫りにしました。
AI学習に使用された書籍が争点に|大手テック企業に対する著作者の訴訟
海外の大手テクノロジー企業に対し、作家らが集団訴訟を起こしました。
訴訟の背景には、対話型AIモデルの開発にあたり、著作権保護下にある約19万冊以上の書籍データが、著者の許可なく学習に使用されたとする主張があります。
この事例は、AIモデルの開発において「学習データの出所と適法性」が問われる象徴的な問題といえます。
AI導入で後悔しないために|企業が押さえるべき3つの基本ポイント
急速に進化する生成AIや業務支援AIの技術。
「生産性が上がるらしい」「トレンドに乗り遅れたくない」と、多くの企業が導入を検討しています。
しかし、勢いで導入した結果、失敗する例も少なくありません。
ここでは、AI導入で後悔しないために、企業が押さえるべき以下3つの基本ポイントを、具体的な視点でご紹介します。
- 導入は“目的”から逆算|最初の設計ミスが後々響く
- AIを活かすカギはデータの質と支える人材
- 見落とされがちなリスク対策|倫理と法令への意識を忘れずに
導入は“目的”から逆算|最初の設計ミスが後々響く
「とりあえず入れる」は危険です。
AIはあくまで“手段”であり、“目的”ではありません。
「話題だから」「他社がやっているから」と目的なき導入をしてしまうと、現場との温度差や成果の不透明さが浮き彫りになります。
コスト削減、生産性向上、顧客満足度の向上など、AI導入の「目的」を明確にすることが重要です。
導入目的が曖昧だと運用や効果測定もブレが生じてしまいます。
まずは、なぜAIを使うのかを言語化するところから始めましょう。
AIを活かすカギはデータの質と支える人材
AIは「データ」であくまで動くため、質・量ともにデータが不十分だと成果は出にくいです。
著作権侵害のリスクも“学習データの不適切な利用”から起こります。
社内で回せないなら、信頼できる外部パートナーの協力も重要です。
とくデザインや広報領域では、プロの関与が“安心材料”になります。
見落とされがちなリスク対策|倫理と法令への意識を忘れずに
AIの出力が「誰かの作品に似ていた」では済まされないケースも多くあります。
そのため、倫理的な懸念、AIに関する法律の整備状況にも注目が必要です。
国内でも今後、生成物の利用範囲・帰属の判断が厳しくなる可能性があり、「活用」だけでなく、「守る」視点がこれからの企業には求められます。
生成AI時代にこそ求められる「専門性」
生成AIは、人間の創造力を拡張する可能性を秘めている一方で、既存の創作物の“積み重ね”の上に成り立っていることも否定できません。
そのためAIは、他者の著作物を学習して酷似した出力を生む可能性があり、著作権侵害のリスクを常に孕んでいるといえます。
またkazeniwa Creative Teamでは、最新の技術とデザイナーによる創造力を掛け合わせ、クオリティと信頼性を両立したクリエイティブを提供しています。
単なるビジュアル制作にとどまらず、著作権や知的財産への配慮も徹底し、安心してご依頼いただける体制も整えています。
参考記事:生成AIとは?一般的なAIとの比較、種類や活用事例を解説|株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン