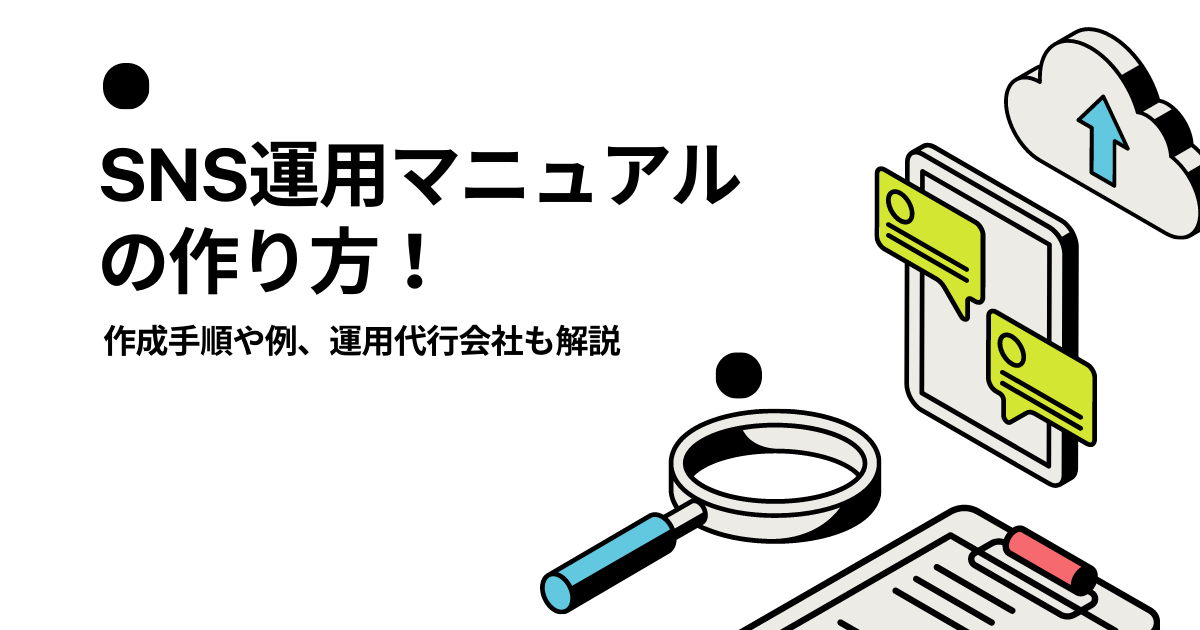インターネット上の誹謗中傷などへの対応を取りまとめた旧・プロバイダー責任制限法は、2024年に情報流通プラットフォーム対処法へと改正、2025年4月に施行されました。
本記事では、旧・プロバイダー責任制限法の改正ポイントとともに、企業のSNS運用における注意点を解説します。
\ テンプレ付き資料! /
今日から真似してすぐに始められます!
プロバイダー責任制限法とは|情報流通プラットフォーム対処法へ2024年改正
プロバイダー責任制限法は「情報流通プラットフォーム対処法」として2024年に改正されました。
インターネット上で人権侵害が発生した際、プロバイダにどのような損害賠償責任が生じるか、範囲や手続き方法を定めています。
なお、正式名称は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」で、情プラ法と略称されます。
関連記事:情報流通プラットフォーム対処法の概要は?SNS利用事業者の義務や注意点を解説
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダー責任制限法)4ポイント
情報流通プラットフォーム対処法のポイントは、下記の4点です。
- プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限
- 発信者情報の開示請求
- 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
- 大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化および運用状況の透明化
プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限
プラットフォーム事業者等(プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等)は、所定の要件を満たしている場合、関係するプラットフォームで誹謗中傷などの投稿をされても免責されます。
プラットフォーム事業者が問われる責任は2種類にわかれており、それぞれ所定の要件は表のとおりです。
| 責任の種類 | 被害者への責任 (権利侵害の情報を削除しなかった場合の責任) | 発信者への責任 (権利侵害していない情報を削除した場合の責任) |
| 免責要件 | 下記に該当しない場合に免責 ・権利侵害の事実を知っていたとき ・権利侵害の事実を知りえたと認められる理由があるとき | 下記に該当する場合に免責 ・権利侵害の情報であると認められる理由があるとき ・削除の申出を発信者へ連絡後、7日以内に反論がないとき |
発信者情報の開示請求
権利侵害に該当する書き込みがあった場合、被害者はプロバイダ等へ発信者情報の開示を求められます。
開示請求の対象となる発信者情報は下記2つに分類されます。
- 特定発信者情報以外の発信者情報
- 特定発信者情報
特定発信者情報とは、侵害情報の通信にかかるIPアドレスやタイムスタンプの情報です。
一方、特定発信者情報以外の発信者情報はアクセスログの詳細(接続履歴、端末識別情報など)やCookie情報、ブラウザやデバイスの情報を指します。
それぞれの情報の開示要件は下記のとおりです。
| 開示要件 | 特定発信者情報以外の発信者情報 | 特定発信者情報 |
| 権利侵害の明白性 | ○ | ○ |
| 開示を受ける正当理由 | ○ | ○ |
| 補充的な要件 | - | ○ |
特定発信者情報のみに適用される「補充的な要件」とは、開示請求をした者が特定発信者情報以外の発信者情報のみでは侵害情報の発信者を特定できない場合などを指します。
参照:総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」
発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
2022年の改正により発信者情報開示命令という新たな裁判手続(非訟手続)が創設され、開示命令の申し立てを1つの手続きで進められるようになりました。
発信者情報開示命令として、一体的な手続きに変更されたことで、より迅速に対応できるほか、被害者の負担を軽減できます。
開示請求は下記の流れでおこないます。
- 発信者情報開示命令申立の準備
- 申立書の作成と提出
- 裁判所での手続き、裁判所からの開示命令の取得
- プロバイダへの情報開示請求
開示請求までは3~6カ月かかるケースが一般的です。
大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化および運用状況の透明化
大規模なプラットフォーム事業者に対して、対応の迅速化と運用状況の透明化を定めています。
大規模プラットフォーム事業者とは、平均月間発信者数が1000万人を超えるSNSプラットフォームを指します。
InstagramやX(旧Twitter)、Facebookなどです。
削除対応の迅速化のために、下記の整備を必要としています。
- 削除申出窓口の整備・公表
- 削除申出への対応体制の整備
- 削除申出に対する判断・通知
また、運用状況の透明化のために、下記項目が必要とされています。
- 削除基準の策定・公表
- 削除した場合、発信者への通知
情報流通プラットフォーム対処法に向けたSNS運用の注意点
SNSを運用する事業者にとって、情報流通プラットフォーム対処法の施行に際し、下記の点の注意が必要です。
- 情報の正確性を担保
- プライバシーの侵害にあたる投稿の回避
- 違法情報の拡散に注意
- 削除要請への対応
- SNSプラットフォームのガイドラインを把握
SNS運用の注意点①|情報の正確性を担保
情報を発信する際は、公的機関の発表や情報源の一次情報の確認をおこないましょう。
誤情報を発信し拡散された場合、マイナスな情報であれば名誉毀損や人権侵害に発展する可能性があります。
誤情報が含まれる投稿が意図せずとも拡散されてしまうと、SNSプラットフォームからのアカウント停止処置や警告の対象となります。
自社アカウントへの信用保持の面でも、情報の正確性を担保することが重要です。
SNS運用の注意点②|プライバシーの侵害にあたる投稿の回避
情報流通プラットフォーム対処法で削除や情報開示請求の対象となりうる、人権侵害にあたる投稿は避けましょう。
個人情報を無断で公開することもプライバシーの侵害で削除対象になります。
人権を侵害する投稿は、開示請求のみならず、被害者からの損害賠償請求など、法的な問題へ発展しかねないため、注意が必要です。
SNS運用の注意点③|違法情報の拡散に注意
第三者の投稿をリポストやリツイートする場合にも、投稿内容の精査が必要です。
近年、SNSを通じた闇バイトの募集や違法薬物の取引も問題となっています。
こうした情報は隠喩を用いた文章で投稿されており、一般人には見分けがつかない場合もあります。
発信者情報が不明など、自社にリスクのある投稿の拡散は避けましょう。
SNS運用の注意点④|削除要請への対応
万が一、自社の投稿に不適切な表現があり、削除要請が出された場合には、迅速な対応が求められます。
SNSプラットフォーム事業者は被害者からの申し出を受けた場合、7日以内に対応を判断し、結果を通知しなければなりません。
プラットフォーム事業者から削除要請された際に対応できるよう、あらかじめ社内でトラブル時の対応方法を共有しておきましょう。
SNS運用の注意点⑤|SNSプラットフォームのガイドラインを把握
各SNSプラットフォームのガイドラインを常に把握しておくことも重要です。
SNSプラットフォームでは運用状況の透明化のために、削除基準を公表しています。
削除対象または人権侵害となりかねない文言のチェックリストを作成したり、適切な文例集をまとめたりして、投稿前に不適切な表現を使用しない仕組みづくりをすすめましょう。
自社がトラブルに巻き込まれた場合の対処
自社が誹謗中傷されたり、不当な書き込みをされたりした場合にも、情報流通プラットフォーム対処法に沿って対処します。
対処法は初動対応と削除申請の2段階に分けて進めます。
トラブルに巻き込まれた場合の対応方法も、SNSアカウントの運用開始とともにマニュアル化し、担当者に共有しておきましょう。
初動対応|削除申請への準備
誹謗中傷などの書き込みがあった場合、初動対応は非常に重要です。
削除申請のために①該当する投稿のスクリーンショット、②投稿ページのURLを保存しましょう。
発信者の情報特定を必要とする場合には、上記①②にくわえて、投稿日時が分かるものが必要です。
多くの場合、投稿に表示されますが、スクリーンショット保存時に確認しましょう。
削除申請|各プラットフォーム窓口へ申請
削除申請の準備ができたら、SNSプラットフォームの窓口へ申請します。
大規模SNSプラットフォーム事業者には通報窓口の設置が義務付けられており、トップページから分かりやすい場所に開設されているはずです。
トラブルに巻き込まれた場合に備えて、マニュアル策定時に、通報窓口の設置場所の確認もしておくとスムーズに対処できます。
削除申請を出しても削除されないなど、被害が続く場合には、発信者情報開示を請求する方法を検討しましょう。
情報流通プラットフォーム対処法はSNS発信を健全にする取り組み
情報流通プラットフォーム対処法は、個人や企業が健全にSNSを活用できるための取り組みです。
自社がトラブルに巻き込まれない、または巻き込まれた際に適切に処置するためには、法律への正確な知識と社内の体制づくりが必要です。
弊社kazeniwaのサービス「SUP」では、最新の法律や社会情勢を踏まえたSNS運用を提供しています。
自社の情報やサービスを健全に発信できるよう、社内の体制づくりから構築してみてはいかがでしょうか。
SNS運用に不安がある、社内体制を見直したい方は、ぜひご相談ください。