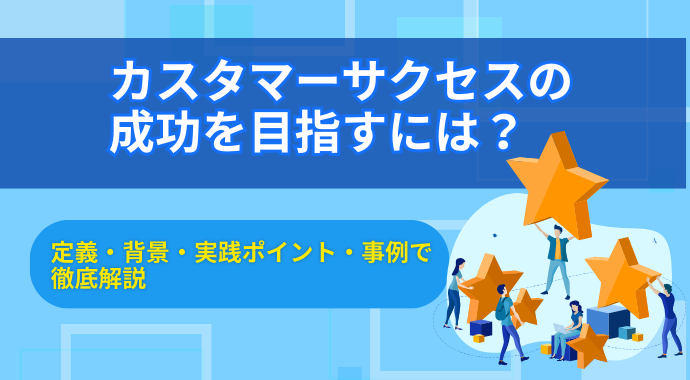SNS利用時間が飽和し、情報発信の「量」では成果が出にくくなっています。
本記事では、ファンコミュニティの最新トレンド(クローズド化・AI運営支援・プラットフォーム進化)をもとに、これからのファン関係をどう再設計すべきかを示します。
\ファンマーケティングの始め方を解説/
資料を無料プレゼント中
ファンコミュニティには関係の再設計が求められている
SNSの利用時間が伸び悩み、ユーザーが「どのブランドに時間を使うか」を選ぶ時代になりました。
DataReportalの調査によると、世界の1人あたりSNS利用時間は2022年をピークに約8〜10%減少し、現在は1日約2時間20分で横ばいとなっています。
つまり「情報の消費時間」はすでに飽和し、発信量だけでは差がつかない局面に入っています。
こうした状況下で、企業やブランドに求められているのは「拡散力」ではなく、 ファンとの関係をどう設計し、どう続けていくかという構造的な視点です。
その設計を実現するためには、トレンドの理解も不可欠です。
トレンドは単なる流行ではなく、「なぜ今その現象が起きているのか」という生活者の行動変化を映す鏡だからです。
マーケティング担当者はトレンドの背景を読み解き、 自社の文脈や関係構造に翻訳して活かすことが求められます。
ファンマーケティングでは、トレンドを理解しながら自社の関係性を再構築することで、長く信頼されるブランド基盤を育てることが大切です。
関連記事:ファンコミュニティとは?目的や成功事例、SNSとの違いを解説
関連記事:コミュニティサイトとは?運営するメリットや注意点、成功のポイントを解説
ファンコミュニティの3大トレンド(2025年10月現在)
注目すべきトレンドはいくつもありますが、ここでは関係構築の変化を象徴する3つの動きに焦点を当てます。
- コミュニティの二層化(オープンSNS × クローズド内側)
- AIによる運営支援(要約・翻訳・安全対策)と共創の高速化
- プラットフォーム内コミュニティ機能の拡張
コミュニティの二層化(オープンSNS × クローズド内側)
SNSの利用時間が頭打ちとなる中、ファンコミュニティは二層構造への変化が加速しています。
オープンなSNSでは「流入」を担い、クローズドな空間では「滞在・共創・収益化」を担う。
この役割分担が、ファンとの関係を維持する前提になっています。
アルゴリズムに左右されない小規模コミュニティの価値が高まり、「誰と、どんな温度感で関わるか」を定義できるブランドほど、継続率やLTVが高い傾向にあります。
ファンは「情報」よりも「つながり」を求めている。
この意識変化が、コミュニティ運営の中心にあります。
関連記事:カスタマーサクセスの成功を目指すには?定義・背景・実践ポイント・事例で徹底解説
関連記事:ロイヤルティプログラムとは?導入メリットと6つの類型・成功事例を紹介
AIによる運営支援(要約・翻訳・安全対策)と共創の高速化
AIがコミュニティ運営を支える仕組みとして急速に定着しています。
Discordでは会話要約・自動モデレーション(AutoMod)などのAI機能が標準化され、YouTubeやBitfanでも翻訳やコメント抽出などAIによる「整流化」が進んでいます。
膨大なやりとりをAIが整理することで、ファンは本質的な「共創(投票・AMA・コラボ)」に時間を使えるようになりました。
AIは熱量を代替するものではなく、人の感情と時間を守る運営基盤として位置づけられています。
関連記事:2025年施行・プロバイダー責任制限法とは|SNS運用企業の対応と注意点
プラットフォーム内コミュニティ機能の拡張
「新しい場所」をつくるのではなく、既存プラットフォーム内でコミュニティ機能を拡張する動きが進んでいます。
YouTubeでは2025年に入り「Community」から「Posts」や新しい“コミュニティ空間”へと進化。
視聴 → 会話 → 課金がYouTube内で完結する流れが定着し、外部に移動せずファンとの関係を深められるようになっています。
これによりファンの離脱を防ぐだけでなく、行動データの一貫管理と世界観の共有を可能にし、継続率とLTVを高める要因になります。
国内で広がるクローズド型ファンコミュニティの潮流
国内でも、オープンSNSとは異なるクローズドなファン空間の形成が加速しています。
特に2023年以降は、「ファンとの関係を内側で運ぶ」ことを前提とした新興サービスが登場し、コミュニティ運営の設計そのものが変化しつつあります。
Nas.io
クリエイターやブランドが自前のコミュニティを簡単に立ち上げられるSaaS型プラットフォームです。
会員管理・課金・メール配信・学習コンテンツ配信をワンストップで備え、無料・有料どちらの形でも柔軟に運用可能。
特徴的なのは「チャレンジ機能」と呼ばれる参加設計で、ブランドが設定したミッションにファンが挑戦し、達成を共有できる仕組みです。
受動的な視聴ではなく参加の必然を生む体験設計を軸にしている点が、従来のSNSとは異なる新しい関係構築の形といえます。
また、外部ツール(LINEやZoomなど)との連携も進み、オープンSNSでの接触からクローズドな滞在・共創への移行を滑らかに支援しています。
PLAYZY
インフルエンサーやクリエイター向けに提供されるコミュニティ×収益化プラットフォームです。
フォロワーが単に情報を受け取るだけでなく、有料コミュニティに参加し、限定コンテンツや特典を通じて応援できる仕組みを備えています。
SNS上でのフォローから一歩踏み込み、「つながる・支える・体験を共有する」関係をデジタル空間内で再現できることが特徴です。
また、インフルエンサー自身が投稿内容や特典を自由に設計できるため、ブランドや個人の世界観を維持したまま関係を深めることが可能です。
関連記事:ファンコミュニティのプラットフォーム一覧付き!SNSとの違いや成功のポイント、注意点を解説
関係を再設計する視点
ファンコミュニティの成功は、「どんな関係を築きたいか」を明確にすることから始まります。
フォローや購買の延長ではなく、「共に考え・つくり・応援する」関係を構造化できるかが鍵です。
そのためには、AMA(Ask Me Anything)や投票企画など、参加を前提とした仕組みを設計し、ブランドとファンの間に双方向の循環(ループ)を生み出す必要があります。
コミュニティの成果は、加入率・継続率・参加率・共創率・収益化率といった指標で段階的に可視化できます。
この流れでKPIを設計すると、どこで熱量が滞っているかを客観的に把握でき、改善の精度が上がります。
トレンドはゴールではなく、関係設計を最適化するための解釈の材料です。
生活者の行動変化を読み解き、自社の文脈に翻訳して運用へ落とし込むこと。
それこそが、変化の速い時代においても長く信頼されるブランド関係を育てる唯一の方法です。
関連記事:SNS運用におけるKPIとは?KGIとの関係や目標設定方法・効果測定方法を解説
関係設計を実践へつなげる
ファンコミュニティのトレンドは、ツールの変化を超えて、ブランドとファンの関係そのものを再構築する動きへと進んでいます。
重要なのは、「どの機能を使うか」ではなく、自社がどんな関係を築きたいのかを定義し、その関係を持続可能な形に設計することです。
そのためには、コミュニティを一過性の施策としてではなく、関係の型づくりを組織として内製化する視点が欠かせません。
ファンコミュニティは、立ち上げよりも継続の方が難しい領域です。
外部の流行を追うだけでなく、自社の文脈に即した関係設計から始めることが、最も確実に成果を生む道です。
弊社 Kazeniwa が提供する DISCO では、企業やブランドのコミュニティ形成を支援し、熱量の高いファンの醸成・獲得や、安定した売上基盤の構築をサポートしています。
ファンとの関係を再設計し、カスタマーサクセスを実現したい方は、ぜひご活用ください。