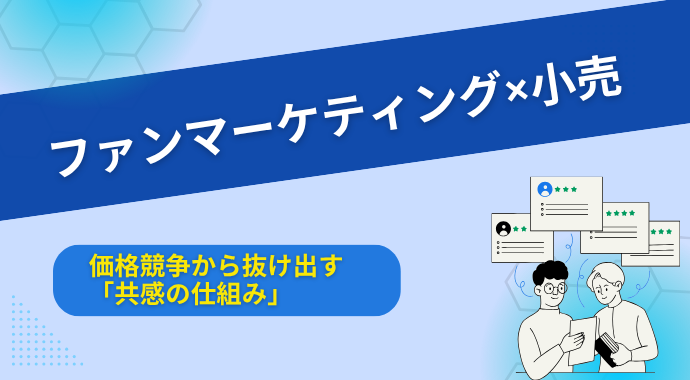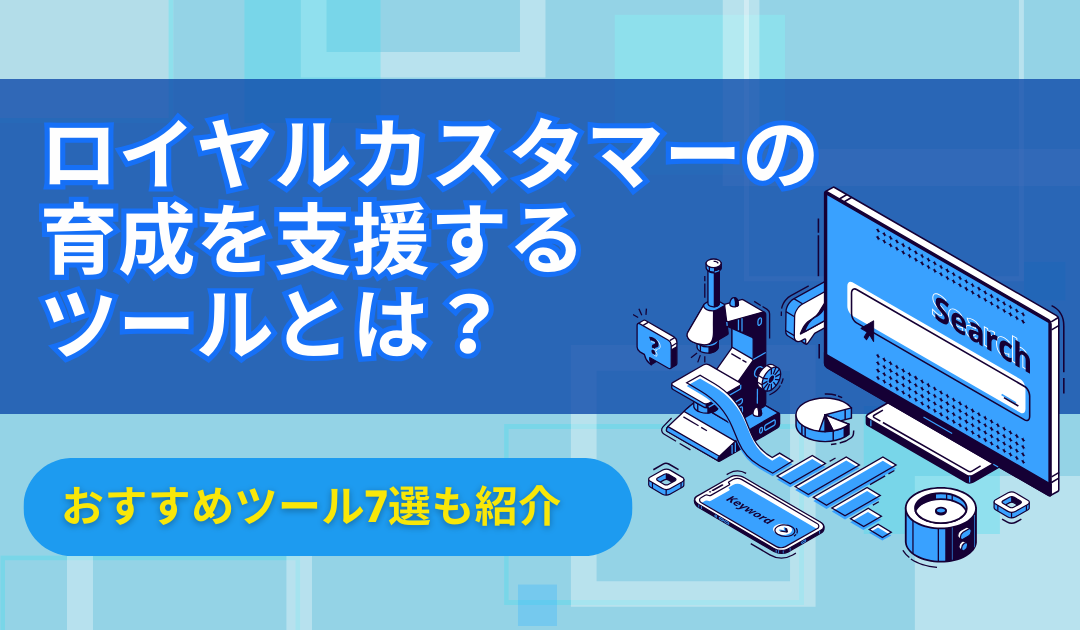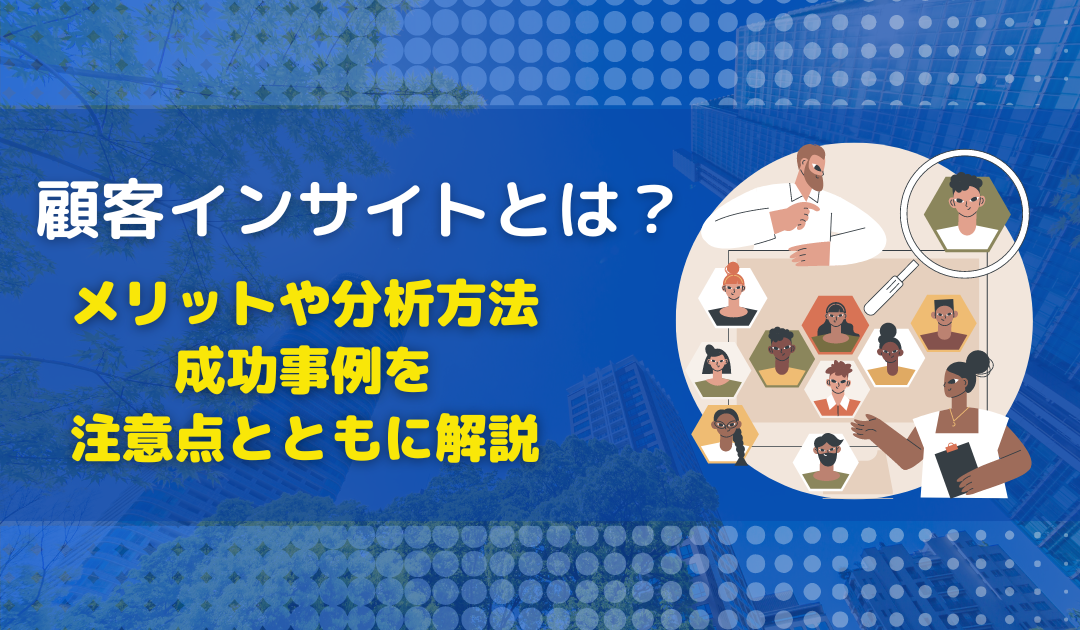SNS発信が飽和する中、小売業には価格ではなく共感で選ばれる理由が求められています。
本記事では、ファンマーケティングを活用し「共感を仕組み化」する考え方を解説します。
小売業が直面する2つの構造的課題
小売業ではこの数年で構造的な課題が顕著になっており、その中でも代表的な2つを解説します。
- 供給過多と価格競争の長期化
- 購買行動のオンライン化による接客役割の変化
供給過多と価格競争の長期化
小売業界では、慢性的な価格競争が続いています。コンビニは全国で約5.6万店(2024年時点)に達し、ドラッグストア市場も年平均5%超の成長を続けています。
食品や日用品を安価に購入できる店舗が至る所に存在する状況は、消費者にとって「どこでも買える」時代を意味します。
また、ディスカウント業態の売上が2桁成長を記録し、低価格志向が加速しています。経済産業省の企業活動基本調査でも、小売業全体の営業利益率が前年より0.2ポイント低下したと報告されており、過当競争が利益を圧迫している実態が明らかです。
購買行動のオンライン化による接客役割の変化
もう一つの構造変化は、購買行動のオンライン化です。経済産業省の最新調査によると、日本のBtoC-EC市場は24.8兆円(前年比+9.2%)、物販EC化率も9.78%に達しました。
ECが生活に浸透し、購買の「比較・検討・情報収集」プロセスの多くがオンライン上で完結するようになっています。
2023年の調査では約5割の消費者がWebルーミング(ネットで調べて店頭で購入)を経験し、6割が今後も取り入れたいと回答しています。
来店時点で顧客はすでに商品知識や価格情報を把握しており、店舗に求められるのは「説明」ではなく、「自分に合う提案や体験支援」です。
スタッフは単なる販売員ではなく、顧客の背景や好みを理解し、ブランド体験を案内する「体験のガイド」としての役割を担うようになっています。
課題を解決する「ファンを育てる仕組み」の重要性
課題を乗り越えるための手段として「ファンを育てる仕組みづくり」が有効です。
- 共感による指名買いをつくる
- 接客やSNS体験を仕組み化する
- 店舗を関係構築の場へ変える
価格競争から抜け出すには「共感による指名買い」が必要
価格ではなく共感で選ばれる状態をつくることが、長期的な収益性の鍵です。同じ商品・価格でも、「この店の考え方や人に共感する」顧客ほどリピート率が高い傾向があります。
たとえば無印良品やスターバックスは、明確な理念と体験を通じて共感による指名買いを生み出しています。
ファンマーケティングは単なる販促手法ではなく、「なぜこの店を選ぶのか」を仕組みで生み出す考え方です。
接客やSNSの体験を仕組み化して継続的に活かす
ファン化は「偶然の好印象」ではなく、「再現できる仕組み」でつくる必要があります。接客やSNS、イベントなど、さまざまな接点で得た顧客情報をCRMやSaaSで蓄積・分析し、体験設計に活かす。
顧客がどの瞬間に共感し、どの体験で離脱したかを見える化することで、感覚に頼らないファンづくりが可能になります。
この仕組みがあってこそ、「誰が担当しても同じ世界観を提供できる」状態が実現します。
店舗を「ファンとの関係を育てる場」に変える
ファンマーケティングの本質は、購買行動のゴールを再定義することです。
店舗を「売る場所」から「関係を深める場所」へ変えることで、再来店や口コミ(UGC)が自然に生まれます。
ファン限定イベントや会員制度、スタッフ発信のSNSなど、「参加したくなる仕掛け」が重要です。
店舗での体験をSNSやレビュー、コミュニティへと連動させると、ファンが自らブランドを広げる循環が生まれます。
関連記事:参加したくなるファンコミュニティサイトとは?企業の世界観でファンを育む戦略
関連記事:ブランドとファンの距離感とは?ファンと良好な関係を築くための考え方や有効な施策を解説
ファンづくりで成果を出す小売企業の共通点
実際に成果を出している企業に共通するのは、ブランドの有無を問わず「信頼を育てる姿勢」です。
- 理念や価値観を伝える努力
- 人の魅力を軸に信頼を築く
- 顧客の声を次の行動に反映する
理念や価値観を「伝える努力」をしている
小売企業や店舗運営者には、ブランドの有無を問わず「選ばれる理由」を明確に伝える姿勢が求められます。
商品の並べ方や店の雰囲気、SNSでの発信トーンなど、あらゆる要素がその店の価値観を表現しています。
たとえば、地域密着の八百屋が「旬を伝える」「生産者とのつながりを届ける」という姿勢を貫くことで、顧客の共感が生まれます。
ファンマーケティングは、ブランドづくりではなく「価値観を共有する仕組みづくり」と言えます。
人の魅力を軸に信頼関係を築いている
店主やスタッフなど、「人の顔が見える小売」はファンを生みやすいです。
接客やSNS発信が顧客との関係性を育て、「この人から買いたい」という感情を生みます。
小売におけるファンマーケティングは、「人」が媒介する信頼経済によって支えられています。
顧客の声や反応を次の行動に反映している
SNSコメントやレビュー、対面での会話など、顧客の反応を拾い、仕入れや陳列、イベント企画に反映しています。
顧客が「自分の意見が活かされた」と感じる体験は、ロイヤルティを高めます。この「聴く→活かす」循環が、ファンが自ら店を応援したくなる原動力になります。
関連記事:ファンマーケティングとSaaSの相性を解説|成果につながる導入メリットと注意点
店舗とデジタルをつなぐ実践施策|現場で始めるファンマーケティング
ここではファンづくりを「現場で実践に落とし込む」ための4つのアプローチを紹介します。
- 顧客情報を一元化して「見える化」する
- 店舗とSNSを連動させる
- ファンが参加できる仕掛けを設計する
- 効果を振り返り改善を続ける
顧客情報を一元化し「見える化」する
会員アプリやLINE公式、POSデータなど、顧客情報が分散しているケースは多く見られます。まずは「誰が・何を・どの頻度で買っているか」を一元管理することが重要です。
購買履歴とSNSでの反応をあわせて見ることで、再来店を促す最適なタイミングが分かります。
CRMやSaaSを活用し、ファンとの関係を「見える化」することが第一歩になります。
店舗×SNSを連動させて「共感の発信源」にする
SNSは販促チャネルではなく、「関係を深める場」として活用することが大切です。
店舗の日常や人の想いを発信し、「この店らしい」世界観を育てます。
投稿は一方通行ではなく、コメントへの返信やリポストなど、顧客との双方向性を意識します。
リアル接客とSNS発信が一体化することで、店舗そのものが共感の発信源になります。
ファンが参加できる仕掛けを設計する
ファンが「自分も関われる」と感じる仕組みをつくることで、関係が一段深まります。
たとえば、限定イベント、試食・試着会、SNS投票、店舗ディスプレイへの参加などがあります。
重要なのは、完璧な企画ではなく、顧客と一緒につくる姿勢を見せることです。
こうした参加体験は、そのままUGC(ユーザー投稿)や口コミへとつながります。
体験の効果を定期的に振り返り、改善サイクルを回す
ファン施策はやりっぱなしにせず、SNS反応率や再来店率などの指標で定期的に振り返ります。 「何が共感を生んだか」をデータで捉え、次の企画に活かします。
小さく試し、改善を積み重ねることで、自社らしいファン育成モデルが形成されます。
関連記事:顧客獲得のためのマーケティング手法とは?便利なツールも紹介
関連記事:新規顧客より既存顧客を優先した方が良いのはなぜ?重視すべき理由やポイントを解説
小売業の共感を仕組み化する
小売業が直面する課題を乗り越えるには、価格や利便性ではなく「共感による指名買い」を生み出す仕組みが必要です。
理念や人の魅力、顧客の声を軸に関係を継続的に育てることで、長期的な信頼が築かれます。
弊社 Kazeniwa が提供する DISCO では、企業やブランドのファンとの関係構築を支援し、熱量の高い顧客の醸成・獲得や、安定した売上基盤の構築をサポートしています。
ファンとの関係を再設計し、持続的なブランド成長を実現したい方は、ぜひご活用ください。